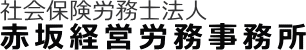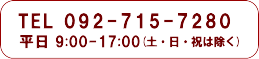採用サポート
![]()

![]() いい人材が採用できない。
いい人材が採用できない。
![]() ミスマッチをなくしたい。
ミスマッチをなくしたい。
![]() 採用後、トラブルがよく起こる。
採用後、トラブルがよく起こる。
![]() 急に退職願を持ってこられる。
急に退職願を持ってこられる。
![]() 必要な人材を採用出来ていない。
必要な人材を採用出来ていない。
![]() 採用業務に時間が割けない。
採用業務に時間が割けない。
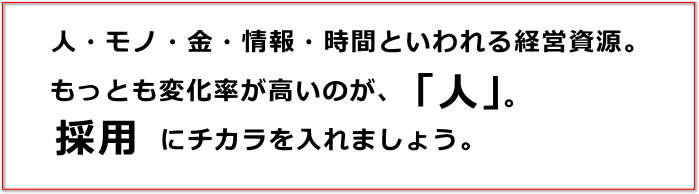
エゴグラム診断
![]()
職場、日常生活を問わず対人関係を改善するうえで、エゴグラムによる分析が役に立つ。
人間には、親・大人・子供の3つの自我状態があり、この3つを行き来している。
親と子供の自我状態はさらに2つずつに分けられ、全部で5つの自我状態になる。
エゴグラムでは5つの自我状態について分析し、自分の行動の特徴を知り、対人関係の中でのより良い行動のありかたを考えるヒントとする。
※自我状態:人柄の機能の表れ
 職場生活や日常生活は対人関係なしには考えられません。特に、職場では対人関係の善し悪しが仕事に影響を与えると言っても過言ではありません。組織における教育の中でも、対人関係に役立つものを考えていく必要があります。
職場生活や日常生活は対人関係なしには考えられません。特に、職場では対人関係の善し悪しが仕事に影響を与えると言っても過言ではありません。組織における教育の中でも、対人関係に役立つものを考えていく必要があります。
ここで紹介するエゴグラムは、1954年、アメリカの心理療法学者エリック・バーンが考えた「交流分析」―TA(Transactional Analysis)の中の1つで、「自我状態」を分析するものです。
(1)ねらいと効果
- 自分を知り、他人を知る力が養われる。
- 自我状態の分析により、自己改善、関係改善のヒントがつかめる。
- 職場におけるコミュニケーションの改善、人間関係の促進に役立つ。
- 対人関係であるため、すべての階層に適用できるし効果も高いものがある。
(2)1人の中に3人の人がいるようだ
ここでは、“人間の心”を「自我状態」と呼んでいます。1人の中に3人の自分[親、大人、子供]がいる、というように考えてください。親と大人と子供の3つの心の状態があって、人間は瞬間瞬間にこの3つの状態を行ったり来たりしているということです。
- 親の自我状態 ……幼少のころ親から教えられた自我で、一言で言うと理想を求め価値基準を重くみる心です。
- 大人の自我状態……現実的にものごとを考える自我で、主体的で冷静な行動をとります。
- 子供の自我状態……本能的、感情的に行動する自我で、生まれたままの自分が現れる部分です。

この3つの自我状態をもう少し細かく分けると、5つの自我状態に分けられます。エゴグラムで分析する場合は、親の自我状態と子供の自我状態を2つに分けて5つの自我状態について分析します。
5つの人柄に関する説明表
| 特徴 | 長所 | 短所 | |
| 批判的親 CP (Critical Parent) |
物事を判断するための基礎となる価値観、理想、信念を身につけてできた部分 | 規律を守る・しつけをする・けじめをつける・評価する・几帳面・道徳的・文化、伝統、習慣を守り伝える・自分に厳しい | 厳格すぎる・圧迫する・圧力をかける・偏見をもつ・口うるさい・堅苦しい・押しつける |
| 保護的親 NP (Nurturing Parent) |
に対する愛情、思いやりを持ち、それを表す行動を見習ってできた部分 | やさしさ・思いやり・世話をする・配慮する・目をかける・心づかい・なぐさめる・元気づける・許す・援助する・相談にのる・保護する | 過保護・過干渉・甘やかす・おせっかい・わがままを許す・相手の自立を妨げる・依頼心を助長する |
| 成人 A (Adult) |
思考力、判断力を基礎に発達する部分で、今どのような状況か、何をしたらよいかなど、事実を冷静に考え、判断する部分 | 冷静・客観的・見通しを立てる・今ここの事実に基づいて判断する・計画する・意志決定する・自分に気づいている | 打算的・冷たい・クール・ビジネスライク・役割人間・味もそっけもない・親密な関係を築けない |
| 自然のこども FC (Free Child) |
人間が本来持っている自分の欲求や感覚、感情を損なわずに強化し、自分の一部とした部分 | 明るい・ノビノビしている・自由・開けっぴろげ・無邪気・天真爛漫・自発的・創造性がある・直感力がある・好奇心が強い・エネルギッシュ・自尊心が高い | わがまま・本能的・自己中心的・衝動的・快楽主義・持続力がない・人のペースを考えない・単純・目立ちたがり・うぬぼれ・我慢できない |
| 順応のこども AC (Adapted Child) |
相手の期待や欲求に添うために自分を抑え、相手に合わせる行動を繰り返して身につけた部分 | 素直・人を信頼する・言うことをよく聞く・従順・しんぼう強い・周囲に合わせる・おだやかひかえめ・協調性がある我慢強い・こつこつやる | 抑圧する・黙り込む・じっと我慢する・閉じこもる・依頼心が強い・顔色をうかがう・こびる・へつらう・くよくよする・自分を責める |
EQテスト
 現代のように価値観が多様化した変化の激しい時代においては、自ら目標を掲げ、他人との調和をはかりながら、自律的に行動できる人間力、すなわちEQが重視されています。この傾向は顕著で、WEB適性検査で最初の選考を行なうなど、EQを採用選考や、社員の教育・評価などに導入するケースが増えています。
現代のように価値観が多様化した変化の激しい時代においては、自ら目標を掲げ、他人との調和をはかりながら、自律的に行動できる人間力、すなわちEQが重視されています。この傾向は顕著で、WEB適性検査で最初の選考を行なうなど、EQを採用選考や、社員の教育・評価などに導入するケースが増えています。
EQ(Emotional Intelligence Quotient)=心の知能指数とは
心の知能指数=EQとは自分の感情を上手に調整し、利用する事で、本来自分が持っている能力を最大限に生かすことが出来る知性のことです。 一般に知能(IQ)が高ければ物事を正確に処理する事ができ仕事が出来る人だと思われがちです。しかし、些細な事に動揺したり、怒ったり、他人の感情に鈍感で全く考慮しないなど、社会的知性の欠けている人だったらどうでしょうか。IQが高いからといってパフォーマンスが充分に発揮でき満足のいく結果が出ているとは限りません。

人間は心理的に動揺すると論理的思考力、記憶力、集中力、判断力、学習能力が低下すると言われています。これを企業でみるならば、生産性の低下、事故の発生といったことにつながります。
総合的な社会的知性=EQが高いと、対人関係能力や自己実現能力も高く、周囲の人から援助や支援を得られやすくなります。つまり、EQが高ければ本来備わっている能力や蓄積してきたノウハウが充分に発揮できる人的環境を自分で作り出す事が可能となります。
EQテストの評価説明
◆ 性格
- 立ち直りの早さ
障害に出会っても望ましくない感情を抑え、衝動を抑える力 - やさしさ
他人への思いやり - 前向きさ
問題を乗り越えて目標を追求する度合い - 誠実さ
自らの業務に対する責任感
◆ 個人的EQスキル
- 自己に対しての認識力
自己の感情とその周りに及ぼす影響の理解度 - 表現力
対人関係において自己の考えを表現する力 - 意思の強さ
卓越した目標達成意欲と向上心 - クリエイティブ
新しいアイデア、方法、情報を自在に扱う力
◆ 社会的EQスキル
- 相手に対しての認識力
他人の感情や考え方を理解、それらに関心を寄せられる度合い - コミュニケーション能力
公平に意見を傾聴し、説得力ある意見を述べる能力 - 協調性
他人と折り合っていける柔軟性 - 順応性(適応力)
機転の利いた判断力や状況判断を下すまでの速さ
◆ その他
- 素質
自己の素質を開花させる素養、可能性
採用試験問題作成
採用試験は次の4科目に分かれています
(1)常識問題
常識問題は就職希望者の「常識」だけをテストすることだけが目的ではありません。
むしろ、就職希望者が、今までどのような生活を送ってきたか、社会のさまざまな出来事にどのように興味をもって活動してきたか、その結果として一般常識をどの程度身につけ、かつ記憶として保持しているかを測ります。
(2)国語問題
 このテストは、一見すると国語の漢字問題に似ています。確かにかなりの部分は国語の知識で解答できます。しかし、反対語の問題など、知識として覚えているというよりも言葉のセンスから解答が求められるようになっています。
このテストは、一見すると国語の漢字問題に似ています。確かにかなりの部分は国語の知識で解答できます。しかし、反対語の問題など、知識として覚えているというよりも言葉のセンスから解答が求められるようになっています。
例えば、「漠然」の反対語「歴然」と暗記している人はいません。「漠然」という単語の意味を知りつつ、その反対語を言葉のセンスでとらえていくわけです。このような問題によって、暗記力ではなく、これまでに磨いてきた言語活動能力を測ることがきるわけです。
(3)英語問題
企業を取り巻く環境は国際化しており、英語の語学力は今後大切な要素になります。しかし、海外要員や輸出入担当者、あるいは外国人と接する機会の多いサービス業でない限り、実際の仕事の中で英語を使うことはほとんどありません。したがって、英語問題は、採用職種、求める能力像に合わせて、取捨選択すればよいでしょう。
しかし、誰でも中学の時から英語の授業を受講しています。そういう意味では、学校での勉学に対する取り組み姿勢、向上心などをみる有効な物差しになります。
(4)理数問題
 すでに成人を迎えた就職希望者について、その知識ではなく知能を測るには、中学、高校レベルの理科・数学・国語が、それに適しているものだとされています。但し、それは、理科・数学の公式や漢字・作家名などを暗記しているかどうかを測るというものではなく、与えられた課題に対し、いかに要領よくスピーディかつ的確に対応していくかという頭の回転力や、暗記でない言語能力を測るわけです。
すでに成人を迎えた就職希望者について、その知識ではなく知能を測るには、中学、高校レベルの理科・数学・国語が、それに適しているものだとされています。但し、それは、理科・数学の公式や漢字・作家名などを暗記しているかどうかを測るというものではなく、与えられた課題に対し、いかに要領よくスピーディかつ的確に対応していくかという頭の回転力や、暗記でない言語能力を測るわけです。
方程式や確率などの問題を、時間内に解かせることによって、課題への要領のいいアプローチとスピーディな処理能力が測れます。優秀な人が1分で解けるものでも、要領の悪い人は15分かかったりします。
採用担当の方へ
●新入社員(新卒・中途)が入社したが、すぐに辞めてしまった
●採用してみたが、思ったような戦力にならなかった

あなたの会社ではこのような経験はありませんか? どんな会社でも多かれ少なかれあるのでしょうが、このようなことが繰り返されていては、せっかく時間と費用をかけても無駄になってしまいます。
「とりあえず来てもらおう」「何とかやってくれるだろう」…で採用していては、一向に改まりません。
「人が採れない、集まらない」と悩んでいる企業がたくさんあります。その理由として「規模が小さいから」「ウチの業界は人気がないから」「労働条件が悪いから」などを上げています。
このような言い訳は、本気で採る気がないのか、採り方が分からないのではないかという気がします。
そこで、中途採用募集の事例を上げて説明致します。
募 集
- 職種 営業(ルート営業)
- 年齢 18歳~35歳まで
- 学歴 高卒以上
- 給与 当社給与規程により優遇いたします
- 待遇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご応募の方は人事担当まで履歴書を郵送するか電話でご連絡ください。
このような募集広告をしばしばみかけますが、これで応募者が集まってくるでしょうか。これでは企業内容は全く分かりませんし、もしこれで応募してくる人がいたとしたら、その応募者はまず使いものにならないでしょう。
求職者には親切にわかりやすく、自社PRをしていくことが大切です。
要は「この会社、仕事はおもしろそうだ」「この会社に入ってみたい」と思わせられるように、いかにつくれるかがポイントです。
まず「採用とは、人と人とのコミュニケーションである」という点をしっかり認識してください。そのことは、求職者への気配りを意味します。
単純に他社の募集広告に合わせて安易な気持ちでつくるから、いくら募集しても良い人が集まらないのです。
自社の製品を売り込むときには最大限のPRを行うのに、人の採用となるとPRを怠る。今は時代が変わっています。他社と同じことをやっていたら良い人材は採れません。「他社との差別化」が必要なのです。
採用の基本は「できるだけ多くの応募者を集めて、その中から優秀な人材だけを採用すること」にあります。
採用面接では人は見抜けない?
「こんなはずじゃなかった・・・」

ある社長が、しばらくしてため息混じりに話していました。
「採用面接では、その人物がすばらしく思えたのに・・・」
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
経営者中心のセミナーでこのことを話したら、ほとんどの人がうなずいていました。
それほど、よくある事なのです。
このことは3つの原因があります。
(1)社長の思い込み
多くの社長は、自分自身が「人を見る目」を持っていると思っています。
これは、社長という地位で、多くの人を見ているからです。 しかし、これは他人のすべてがわかるわけではないのです。 特に、面接という特殊な場面での影響を考えないといけません。
採用したい人物像が頭にあるので、本人を客観視できません。 目の前の人が、採用したい人物に見えてくるのです。
そして、判断しているケースが多いのです。
(2)見た目の印象
見た目の印象は大事です。
「人は見た目が9割・・・」このような本も多く出版されています。
見た目の印象は、重要な要素です。
しかし、この印象ばかりに引きずられていると誤解が生じます。
2回目にあったときに、第一印象と異なるイメージの場合は、1回目の面接が不足していたのかもしれません。
(3)書類にひきづられる
「大企業に勤めていれば、優秀である」
「高学歴であれば、優秀な人材だ」 このような思い込みが面接側にあります。
特に、書類選考で事前に履歴書や職務経歴書があれば、記憶は固定されてしまいます。
(1)と同じですが、特に書類だと影響が大きいです。
記憶は薄れますが、書類は残っているからです。
以上の原因をクリアするには・・・。
いくつかのポイントを気をつければ、回避できます。
まずは、チェックリストの作成です。

これは聞きたいことを事前にリスト化し、漏れのないようにします。
面接が終了後に「聞き忘れた・・・」ということがないようにします。
そして、印象に引きずられる事が少なくなります。
採用する人物の業務を明確にする。
「優秀な人がいたら採用する」と思っている社長は本気ではないのです。
具体的にお願いする業務を明確にする必要があります。
すると、漠然とした人物像より具体的な人物像が浮かび上がります。
さらに、面接時に相手にいろいろ話をしてもらうことです。
話をすることは、緊張を和らげる効果があります。
それから、話を瞬時にまとめなくてはならないので、考え方もわかります。
いろいろな質問から、相手に話をしてもらいましょう。
書類の判断よりも、話している本人について耳を傾けましょう。
瞬時に人を判断することは大変難しいことです。
自社の魅力を引き出す
どんな会社でも魅力のない会社はありません。採用に成功していない会社はえてして自社の魅力が分かっていないようです。自社の特長や魅力が分かっていないと、満足な企業PRもできませんし、説得力もありません。
勿論、企業の魅力や特長とは、入社する者にとってであることはいうまでもありません。
「うちの会社は魅力なんか無いよ、小さいし、給料は安いし、休みは少ないし、仕事は3Kだし」。当然のごとく、採用に成功していない会社からはこのような反論がでてきます。
では逆に、そんなにすべてが整っている会社がどこにあるのでしょうか。また、何を基準に給料が少ない、休みが少ないといわれるのでしょうか。
それは、他社と比べて、といわれるでしょうが、仕事の疲労度、実際の勤務時間などを考えると、どこもそれほど差がないのが現状です。
一例をあげますと、全国展開している、ある大手企業があったとします。この企業では当然全国的な人事異動がありますので、社員はいつどこに転勤になるのか不安でたまりません。しかし小さくて一つしか事業所がない会社に転勤はありません。ましてや今は長男・長女の時代、これだけでも大手企業よりはるかに有利になるのではないでしょうか。
うちは転勤があるので人を集めにくい、と悩んでいる大手企業もたくさんあるということと、特別考えもしなかったこんなことでも訴えていける要素があるということを頭に入れておく必要があります。
1.特色や魅力を要素ごとに分類してみる
- 大きさ、規模

- 職 種
- 労働条件
- 社会的貢献
- 将来性
- 社 風
- 安定性
- 福利厚生
- 通 勤
- 技 術
- 教 育
- その他
2.特色や魅力を表現してみる
事例Ⅰ 数十人程度の中小企業(製造業)で大卒文系を採用したい場合
- こんな製品をつくり社会に貢献しています
- 市場の将来性はこれから、大きく伸びるチャンスを秘めた会社です
- そのため、これから積極的に若い人材を採用していきたい
- ですから、それぞれが役員になれるチャンスが十分にあります
- 会社と共に大きく成長しましょう
事例Ⅱ 建設関係で現業職を採用したい場合
- これからは手に職をつける時代、どんな時代になっても専門的技術を身につけていれ ばどこでも通用します
- そうした中で○○年以上の経験を積めば国家試験が受験できます
- 資格をとれば鬼に金棒、資格取得は会社でバックアップします
- 実務をこなしているので試験は決して難しくありません
- 将来、希望により独立も可能です
- 専門技術職ですから普通の仕事と比べて給料も数段上です
- 仲間同士気の合う明るい会社です
以上、2つの事例をあげてみましたが、もっと良い表現があるかもしれません。しかし、このようにPRするだけでも、かなり採用力が変わってくるはずです。
相手の考えていることをよく知ったうえでPRしていけば、必ずや成功に至ること間違いなしです。敵の戦力も味方の戦力もわからずに、ただやみくもに突撃しても戦争に勝てるはずはありません。世の中、情報氾濫化時代です。この時代、いかに効果的なPRができるかどうかが成功の鍵をにぎっているといえましょう。
会社説明会で重点的に説明する事項
- 経営(会社)の概要
- 経営理念、経営方針
- 仕事の内容
- 採用予定人員
- 採用後の処遇、労働条件
(初任給、賞与、退職金、労働時間、休日、休暇、福利厚生等) - 勤務地
- 期待する人物像
- 採用選考のスケジュール
(書類選考、筆記試験、面接などをいつ行うか) - アンケート